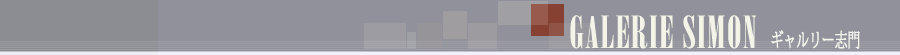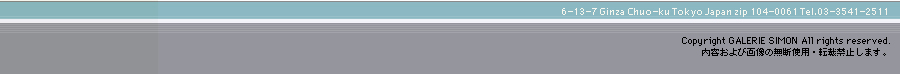|
彫刻家と素材との関係は常に危ういバランスの上にある。とりわけ木のように、それ自体、強い表現力を持つ素材を選択する場合、作家のその素材に対する親和性や抵抗感、言い換えれば自らの心理的な距離が、作品の方向性を自ずと決定するといっても過言ではない。
柳川貴司が木彫に集中するようになったのは1990年頃からであるが、木に対する意識に新たな展開が見られるようになるのは2000年代中頃、ちょうど今
回の発表作品でもある「すむところ」シリーズがスタートした時期である。それまでは人体を思わせる具象彫刻を手掛けていた柳川であったが、この頃からフォ
ルムは単純化され抽象性が高まっていく。かつては彩色されていた木の表面は、手つかずのままに残され、年輪や木目が浮かび上がるようになった。
さらに制作方法にも微妙な変化が訪れる。大型の木彫をつくる作家にとって、複数の木材を隙間なく組み合わせ一体化させてから彫るというプロセスは欠かせ
ないが、この時期から柳川の意識は「一体化させる」ことよりもむしろ、木を「寄せる」という方向にシフトする。例えば2006年に発表された≪すむところ
Ⅰ≫は、ヒマラヤ杉の丸太を同心円状に25本も寄せ合わせ、一つの円柱のフォルムにまとめたものであるが、本来は鑑賞者の目に留まらないように隠されるべ
き木と木の境目や隙間が、ここではクローズアップされるような形で全体に組み込まれ、「寄せる」構造自体がそのまま力強い表現となっているのである。
言うまでもなく木は一つとして同じものはない。大きさ、色はもちろんのこと、ねじり、そり、縮み、あばれなどそれぞれにクセがあり、「寄せる」といって
も容易ではないのだが、柳川はそれを力技でねじ伏せるのではなく、木一つ一つの声に丁寧に耳を澄まし、その性質を見極め、隣り合う木同士を無理なく寄り添
わせる。であるからこそ、作品には個々の木の語りが豊かに内包され、われわれを”木をめぐる思策”へと導くのである。
しかし、柳川はただ従順に木に「寄り添う」というわけではない。今回発表される≪すむところVI≫において、作家は年輪の優美な曲線をこれまで通り温存
しつつも、作品全体としては緊張感あるフォルムを生み出している。大きく開いた半球状のパーツが、やや小ぶりの円柱の上に乗せられたこの彫刻は、重さと軽
さ、集中と拡散といった相反する感覚を同時に誘発し、鑑賞者の知覚に絶えず揺さぶりをかける。この微妙な均衡状態にある彫刻の中に、素材に対する親和性を
超えてなお溢れ出るフォルムへの拘りを感じとることもできよう。柳川は現段階で、素材への「寄り添い」から
「駆け引き」へと駒を進めているようにも思える。
「すむところ」シリーズにおいてここ数年、急激な展開を見せる柳川は、「今の作品の中に次の作品の種が潜んでいる」という。作家と素材との関係性―その危ういバランスは絶えず変化し、この不可視のせめぎ合いの中にこそ次なる存在が立ち現れる。
テキスト:森千花/東京都現代美術館 学芸員(柳川貴司展カタログより) ※転写コピー禁止
|
|